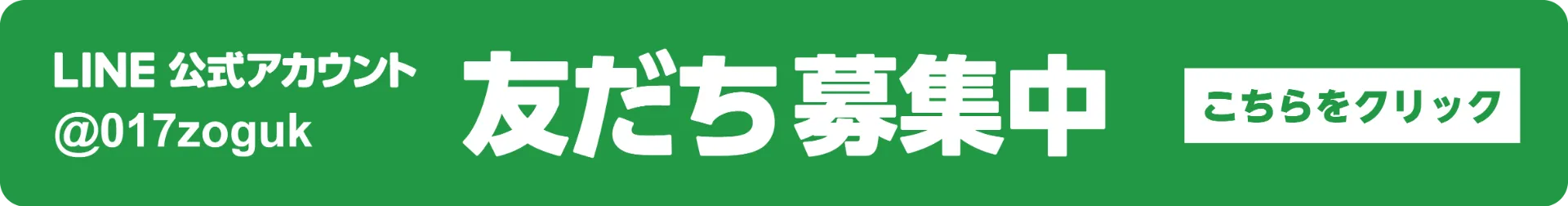専門医による骨活解説
2025/07/29
こんにちは、整形外科専門医の金井です。今回は「栄養から考える骨活」について、4つの栄養素(タンパク質、カルシウム、ビタミンD、ビタミンK)の視点からご紹介します。骨の健康に直結する栄養バランスを、わかりやすく整理しました。
●骨の“構造材”となるタンパク質
骨を形作る基盤となるのがタンパク質です。筋肉と同じく、骨自体もタンパク質を豊富に含んでいます。実際、体重1kgあたり約1.2gを目安に毎日、数回に分けて摂取することで効率よく骨の素材を補えます。なお、腎機能に制限がある方は医師と相談を。主な供給源には肉、魚、大豆製品(納豆・豆腐など)があります。
●骨の“材料”カルシウム
カルシウムは骨の硬さや密度を支える重要な役割を果たします。しかし単体での吸収効率は低いため、ビタミンDや一部発酵食品などと同時に摂取するのが効果的です。厚生労働省の目安では、食事から700~800mg/日が理想とされますが、我が国では平均的に約517mg/日で、約200mgが不足している実情です。海藻、小魚、乳製品、野菜、豆類などは優れた供給源です。
●カルシウム吸収を促すビタミンD
ビタミンDは腸でのカルシウム吸収を助け、骨の代謝調整にも関与します。天然型は肝臓・腎臓を経て活性化される形で作用し、体内に蓄えられるため、週単位の摂取で貯蓄が可能です。ただし、肝腎機能が低下している方では、その吸収に注意が必要です。目安摂取量は15〜20μg/日程度(週105μg)、平均摂取量は7.3μg/日とされており、不足気味な傾向があります。青魚、きのこ類、日光浴などが主な供給源です。
●骨内部の質を整えるビタミンK
最後に、ビタミンKは骨たんぱくである“オステオカルシン”の働きを支える調整役です。通常の食事で充足しやすい一方、納豆や緑黄色野菜を避ける生活習慣では不足の可能性があります。目安は250〜300μg/日で、主に納豆、ブロッコリー、小松菜、春菊などに豊富です。ただし、ワルファリンなどの抗凝固薬を服用中の方は注意が必要です。
●まとめ:バランスを意識した骨活を
4大栄養素の特徴を総括しますと、
タンパク質=骨の“足場”を作る
カルシウム=骨の“硬さと密度”の源泉
ビタミンD=吸収と代謝をサポート
ビタミンK=骨の質を整える調整役
特に、食事から十分なカルシウムとビタミンDを補うことが鍵となり、タンパク質も1日分をこまめに摂ることで骨の素材が安定します。ビタミンKは通常の食事でほぼ充足できますが、偏食や特定食材を避ける方は補足を意識してください。
骨の健康は、日々の積み重ねから。意識的に食事を整えることが、未来の骨を強くしなやかにする第一歩となります。
----------------------------------------------------------------------
コツコツグルメ
神奈川県川崎市高津区梶ケ谷3丁目16-14
FAX番号 : 044-948-5292
健康食品で骨粗鬆症の予防が可能
カルシウムが豊富な健康食品
ミネラルが豊富に含んだ健康食品
健康食品で骨粗鬆症の予防
冷凍で美味しい健康食品を提供
----------------------------------------------------------------------